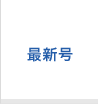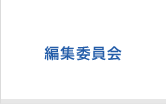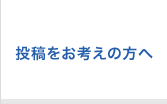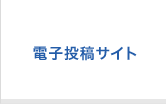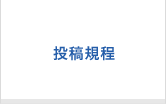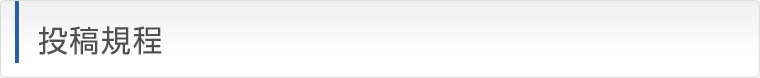- ホーム
- 投稿規程
臨床神経学 投稿規程(2024年9月1日改定)
投稿規程は適宜改定されるので,本誌最新号掲載の投稿規程に従う事.
原稿は専用の原稿テンプレートを使用して作成ください.原稿テンプレートは下のリンクからダウンロードしてください.(原稿テンプレートがない投稿種別については,投稿規程に従い,Wordで作成ください.)
A)投稿原稿の募集と審査
- 国内外の他雑誌に掲載されていない論文あるいは現在投稿中でない論文に限る.
- 投稿論文の採否は編集委員会で決定する.
- 和文及び英文の原稿を受け付ける.
- 日本神経学会会員以外の投稿も受け付ける.
- 本誌の採用論文は一般公開する.会員限定の論文は受け付けない.
- 地方会会長推薦論文も査読を行い採否を決定する.採択を約束するものではない.
- 本誌に一度不採択になった論文の投稿は受け付けない.
B)個人情報保護と医学研究に関する指針遵守
- 「個人情報・医学研究に関する指針チェックリスト」を確認する.
- 患者の同意書が必要とされる場合は,「患者同意書」を患者から取得して提出する.原本は必ず手元で保管すること.特に患者が特定される身体写真(顔写真, 頭部のほぼ全体がはいるものは該当.身体の一部やMRI 画像は非該当)については,実際に掲載される画像, 動画を患者が確認し,Legends に「Fig. ○ is published with patient’s permission./ 患者の許可を得て掲載」と記載すること.また,意識障害や認知症などにより当該個人より同意書を得ることが困難な場合は,適切な代諾者(配偶者,親,子,後見人など)の同意でもよい.患者の同意を代筆者(配偶者,親,子,後見人など) が署名してもよい.本人が死亡している場合は遺族の同意書を得ること.複数の患者・家族からの同意書が必要な場合は,全員から取得すること.判断が困難な場合は編集委員会へ連絡をして確認すること.
- 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などにより該当する,施設における倫理委員会の承認が必要とされる研究については,倫理委員会で承認済みであること及びその承認番号と承認日を論文(方法)に記載する.自施設内に倫理委員会が設置されていない場合は,設置されている他施設に審査を依頼し,承認を得る.
- 自施設内での後ろ向き疫学あるいは臨床観察研究でも倫理委員会承認が必要である.(厚生労働省疫学研究に関する倫理指針」についてのQ&A Q1-3(1)を参照のこと).
- 投稿から出版までの過程で論文に疑義が生じた場合は,編集委員会から筆頭著者あるいは当該施設へ問合せることがある.
C)COI状態の自己申告
- 投稿する著者全員は,会員,非会員を問わず論文内容に関係する企業・組織や団体との投稿時から遡って1年間のCOI状態を「自己申告によるCOI報告書」に記載して提出する.
- 採択となった論文の本文末尾に,自己申告したCOI状態を,筆頭著者,共著者ごとにすべて掲載する.
- 薬剤及び医療機器に関する論文はCOIの申告内容について,編集委員会から問合せることがある.
- 企業に雇用されている著者による自社製品についての論文は,想定されるバイアスリスクについて編集委員会が厳格なCOIマネージメントを行う.
- 企業に雇用されている著者が含まれる論文は,COI開示に加え,論文の具体的なContribution(どの範囲を担当したかまで詳細に)も明記する.(Dの13.の項 参照)
- 重大なCOI状態にあると疑義が想定される自己申告については,日本神経学会COI委員会で検討する.
D)投稿の形式
- 邦文の投稿の形式は総説,原著,症例報告,短報,Picture in Neurology,Letters to the Editor,提案・試案,委員会等報告として受け付ける.
-
原稿の構成は表紙/要旨/本文/引用文献/英文抄録/Figure/Table/Legendsからなる.下記に示す制限と投稿規程E)執筆要項を遵守して,原稿テンプレートを使用して作成すること.
和文原稿に関する制限※ 総説 原著 症例報告 短報 Picture in Neurology Letters to the Editor 著者人数 10名以内 10名以内 6名以内 6名以内 5名以内 3名以内 要旨(300字以内)と本文
(Legendsは含めない)の合計文字数7,000字以内 7,000字以内 5,000字以内 2,800字以内 要旨無/
1,000字以内要旨無/
1,600字以内英文抄録単語数 300単語以内 300単語以内 300単語以内 200単語以内 無し 無し Figure/Tableの数 8個以内 8個以内 6個以内 2個以内 1個以内
(組写真可)1個以内 文献数 30編以上可 30編以内 30編以内 10編以内 5編以内 5編以内(1編は対象となる掲載論文) - 依頼総説:上記表の総説に準ずるが,合計文字数・Figure/Tableの数については制限を超えても認める場合がある.又, Figure/Table及びLegendsは原則英文で表記するが,教育的な理由で和文表記を希望する場合は,その旨を申し出ていただき,内容を編集委員会幹事および副委員長,委員長が判断し認める場合がある.
- Picture in Neurology:教育的意義のある各種神経画像検査(MRI,CT,核医学検査,血管造影検査,超音波検査など)や病理・脳波・臨床写真等の静止画像を掲載するもの.原稿の構成は表紙/本文(症例,考察)/引用文献/Figure/Legendsからなる.
- Letters to the Editor:本欄は過去に本誌に掲載された論文に対する各種の意見(批判,討議など)を書簡の形式で書く.(投稿年月日,拝啓―――敬具)
- 提案・試案:制限は上記表の原著に準ずる.
- 委員会等報告:日本神経学会の各種委員会など公式の組織体(セクションを含む)が行なった事業・活動(セミナー・シンポジウム等の行事を含む)についての公式な報告を掲載するもの.委員会等報告を投稿しようとする場合は,当該事業内容および掲載予定の報告概要(要旨あるいは趣旨でもよい)について,担当委員会および理事会に報告し了承を得ておくこと.委員全員を著者とせず,報告内容に関与した委員のみを著者としても良いが(委員でない関与者の追加も可),著者の最後に委員会(組織体)名を記載する.原稿に関する制限は上記表の総説に準ずるが,合計文字数・Figure/Table数,著者人数は制限を超えてもよい.又, Figure/Table及びLegendsは原則英文で表記するが,教育的な理由で和文表記を希望する場合は,その旨を申し出ていただき,内容を編集委員会幹事および副委員長,委員長が判断し認める場合がある.
- 英文の投稿の形式は総説,原著,症例報告,短報,Picture in Neurology,Letters to the Editorとして受け付ける.
-
英文の投稿はnative speakerの校閲を受けその証明書を添付する.
英文原稿に関する制限※ 総説 原著 症例報告 短報 Picture in Neurology Letters to the Editor 著者人数 10名以内 10名以内 6名以内 6名以内 5名以内 3名以内 英文抄録単語数 300単語以内 300単語以内 300単語以内 200単語以内 無し 無し 本文の単語数 3,000単語以内 3,000単語以内 2,000単語以内 1,000単語以内 500単語以内 500単語以内 Figure/Tableの数 8個以内 8個以内 6個以内 2個以内 1個以内
(組写真可)1個以内 文献数 30編以上可 30編以内 30編以内 10編以内 5編以内 5編以内(1編は対象となる掲載論文) -
著者の条件:著者は下記の医学雑誌編集者国際委員会の定める論文著者の基準を満たすこと.Gift authorship,ghost authorshipは認められない.特に,単に同じ施設や研究室に所属しているというだけの理由で著者に加えるgift authorshipは重大なauthorship違反である.
医学雑誌編集者国際委員会の定める論文著者の基準:
論文著者として名前が掲載されるためには,以下の1)〜4)のすべての項目に該当していなければならない.- 1) 研究の構想・立案,データの収集,あるいはデータの解析および解析結果の解釈のいずれかに実質的に貢献している.
- 2) 論文の原稿を書くか,その論文の内容に関わる極めて重要な校正・改訂作業(リバイズ)にかかわっている.
- 3) 掲載される最終版の原稿の中身を理解し,承認している.
- 4) 論文のあらゆる側面について,論文の正確性・真正性に疑義が寄せられたときに適切に説明することができる.
なお,症例報告において診断の根拠となるなど,提供されたデータが論文の主旨と関わる場合は,原則としてデータ提供者を著者とし,論文作成段階から緊密な意見交換を行うこと.
前掲の著者人数の制限は極力遵守すべきであるが,上記の論文著者の基準を厳格に満たす者がこの制限を越える場合には,各著者の論文作成における役割を記載し,制限人数を超える著者数となった理由を明記した文書(書式自由)を提出すること. -
生成系AI(大規模言語モデル)使用について
- 11-1.
- 大規模言語モデルを使用した著者は,原稿の最後,引用文献のすぐ上に,使用したツールとその理由を明記する.例 “XXXXのため,XXXXを使用した”.
- 11-2.
- 大規模言語モデルは著者としては認めない.
- 11-3.
- 大規模言語モデルで作成された図について,画像剽窃の疑いが払拭できなければ使用できない(オリジナルを個人で作成し,AIに依頼して整えた場合は使用できる).しかし,画像の作成や改変に大規模言語モデルを使用することが,研究計画や研究手法の一部である場合は例外とする.
- 11-4.
- ここで論じる物には,文法チェッカーや引用文献マネージャーは含まない.
-
謝辞
論文への貢献がある者で著者の条件(10.の項参照)を満たさない場合には,謝辞欄に所属,氏名,貢献内容を示す.図表等のデータ提供者に対して謝辞を入れる場合には,著作権等の問題が生じないように,必ずデータ提供者から事前に同意を得る.当該論文の研究遂行に使用した資金源を明らかにする必要がある場合,企業からライティングサポートを受けている場合も謝辞欄に記載する. -
Contribution
企業に雇用されている著者が含まれる論文は,COI開示に加え,論文の具体的なContributionを明記する.著者毎にどの範囲を担当したかまで詳細に記載する. -
追悼文:日本神経学会会員で多大な貢献をされた医師,研究者の追悼文を掲載する.追悼文の対象者は日本神経学会役員のうち,名誉会員,功労会員,学術大会長,理事,監事とする.投稿にあたっては,事前に編集委員会に連絡し投稿の許可を得ること.編集委員会の許可を得た後にご遺族の許可を得ること.著者からの投稿以外に,編集委員長から依頼する場合もある.追悼文は「追悼文投稿フォーム」を用いて作成する.内容に関しては,著者が最終責任を有する.投稿された追悼文に関する掲載の最終決定は編集委員長が有する.刷り上がりは1ページとし,分量に応じた修正などを行うことがある.
著者人数 1名 要旨 不要 英文抄録 不要 本文文字数 3000文字以内 Figure/Tableの数 1個(対象者の肖像などお顔のわかるもの) 文献数 5個以内 - 施設紹介:掲載論文数が多かった施設は,臨床神経学に投稿する為に取り組んでいる事等を纏めた紹介文を掲載する.著者からの投稿は受け付けず,編集委員長から該当施設の責任者に投稿を依頼する.投稿された紹介文に関する掲載の最終決定は編集委員会幹事および副委員長,委員長が行う.刷り上がりは1ページとし,分量に応じた修正などを行うことがある. 著者の人数,文字数,図表の数等は追悼文に準ずる.
- 留学報告:日本神経学会海外派遣プログラムの支援を受けた会員が,帰国後の義務として提出した報告書を掲載する.投稿された留学報告に関する掲載の最終決定は編集委員会幹事および副委員長,委員長が行う.著者の人数,文字数等は追悼文に準ずるが,図表は2個以内とする.
E)執筆要項
原稿は以下の規程に従い原稿テンプレートを使用して作成すること.フォントは和文は,MS明朝,MSゴシック,英文はTimes,Times New Roman,Arialといった標準フォントを用いること.フォントのサイズは10.5〜12ポイントとする.
- 表紙
- 1-1.
- 表紙は原稿テンプレートに従い和文で表題,著者名,所属,連絡先,和文キーワード(5個以内,Letters to the Editor,提案・試案は不要)ランニングタイトル(全角で46文字/半角で92文字以内)を記載する.
- 1-2.
- 表題は50文字以内(英字は2lettersを1文字で換算)を目安とする.略語は神経学用語集にあるものは使用可.但し,神経学分野で広く使用されているものはこの限りではない.
- 1-3.
- 筆頭著者の所属は,その研究が行われた施設とする.
- 要旨 和文の要旨を300字以内で記載する(Picture in Neurology,Letters to the Editorは不要).
- 本文
- 3-1.
- 本文は原則として1)前文,2)対象・方法,3)結果・成績,4)考察,から構成される.症例報告,短報の場合は,「はじめに」「症例:」「主訴:」「既往歴:」「家族歴:」「現病歴:」の順に記述する.記述の仕方は,「症例:」「主訴:」の部分は体言止めとし,「症例:xx歳,女性 主訴:頭痛」など記述し,論文要旨と「症例:」「主訴:」以外の本文は「〜であった.」「〜した.」「〜と考えた.」などと記述し,体言止めは避ける.現病歴,所見,経過等の症例記載は全て過去形とする.
- 3-2.
-
神経学用語については日本神経学会の「神経学用語集」に従う.
但し,抗体に前置される単語が抗原であることが自明であり,冒頭の『抗』を省いても意味に混乱をきたさない場合にはこれを省略してよい. - 3-3.
- 日付は,臨床経過を知る上で必要となることが多いので,個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい.もしくは「発症○ヵ月後,発症○ヵ月前」や年齢で記載する.
- 3-4.
- 外国語の固有名詞(人名,地名):原語(アルファベット)で表記し,頭文字は大文字とする.ただし,日本語化しているものはなるべくカタカナ表記とする.
- 3-5.
- 外国語の単語(症候名,病名,その他):原語(アルファベット)で表記し,頭文字は,ドイツ語名詞および文頭の場合を除きすべて小文字とする.日本語として定着しているものはカタカナ表記とする.(例 レム睡眠,運動ニューロン,アテトーシス(アテトーゼ),ミオクローヌス,ニューロパチー,ミオパチー)
- 3-6.
- 英語と日本語の選択:欧語表現と日本語表現の両者が考えられる場合,日本語として定着している場合には日本語表現を用いることとする.(例 hyperesthesia→感覚過敏,dysarthria→構音障害,winged scapula→翼状肩甲,putamen→被殻)
- 3-7.
- 薬品名,化学物質:日本での慣用に従ったカタカナ表記とする.薬品名は商品名ではなく一般名で表記すること.(例 ガバペンチン,塩酸エペリゾン)日本語として慣用化していないものは,原語で表記する.(例 mitoxantrone(MIT),rituximab)
- 3-8.
- 動物,植物名など:人も含めて動物種,日本語化外来語はカタカナ,それ以外はひらがなとする.(例 イヌ,ブタ).但し特定の動物や植物を示す場合は,学名を用いること.
- 3-9.
- 脳脊髄液:圧__mmH2O,細胞数: /mm3もしくは/μlであらわす.細胞種類は,単核球,多形核球の別に記載する.
- 3-10.
- 数字:算用数字を用い,度量衡単位は一般的な以下のものを使用する(m,cm,cm2,l,dl,μl,kg,g,mg,μg,ngなど).
- 3-11.
- 略語:初出時にフルスペルと略語を併記し,以後,略語を使用すること.(日本語例 筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis,以下ALSと略記), 英語例 amyotrophic lateral sclerosis (ALS) ).Figure/Tableにおいても略語には説明を付ける.
- 引用文献
- 4-1.
- 引用文献は本文に引用されているもののみをあげ,引用番号は本文の引用順による.本文中の引用箇所に番号をつける(肩番号の必要はない).
- 4-2.
-
引用文献作成支援のためのEndNoteのスタイルテンプレートを下記よりダウンロードすることができる.引用文献の最新の書き方は規程の4‐3に従うこと.
臨床神経学 EndNoteスタイルテンプレート
EndNote「臨床神経学」のアウトプットスタイルの使用方法 - 4-3.
-
引用文献の書き方はバンクーバースタイルに準じる.ただし引用文献の著者氏名,編者氏名は,4名以上の場合は最初の3名を書き,他は―ら,または,et alとする.また最終頁数は略さず全数字を記載する(例:135-46→135-146).抄録の引用は表題の最後に(会),欧文発表の場合は(abstr)とする.in press論文を引用する場合は,採択通知及び,採択されたオリジナル原稿全文を投稿添付書類としてアップロードする.
引用文献の記載項目と記載例 記載項目(それぞれの間に半角スペースを入れるが,雑誌の「年;巻:頁-頁.」の間にはスペースを入れない) 雑誌 著者名.表題.雑誌名 年;巻:頁-頁.
早期公開は,著者名.表題.雑誌名Advance Publication, 年;doi.和文例:里吉営二郎.内分泌障害によるミオパチー.臨床神経 1961;1:439-449. - 英文例:
- McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 2005;65:1863-1872.
- 早期公開例:
- 安東由喜雄.アミロイドーシスと神経疾患:治す神経内科疾患の実践.臨床神経Advance Publication,2015; http://doi.org/10.5692/clinicalneurol.cn-000775.
書籍 著者名.表題.編者名.書名.版数,発行都市名:出版社名; 年.頁. - 和文例:
- 鈴木重明.重症筋無力症.鈴木則宏編.神経内科研修ノート.東京:診断と治療社;2014.p.537-540.
- 英文例:
- Meldrum BS, Corsellis JAN. Epilepsy. In: Adams JH, Corsellis JAN, editors. Greenfield’s neuropathology. 4th ed. London: Arnold; 1984. p. 921-950.
ガイドライン 編集.ガイドライン名.版数,発行都市名:出版社名; 年.頁. パーキンソン病治療ガイドライン作成委員会編.パーキンソン病治療ガイドライン2011.東京:医学書院; 2011. p. 2-4. 研究報告 著者名.表題.編者名,研究班名,報告書名.年.頁. 瀧山嘉久,辻 省次,佐々木秀直ら.痙性対麻痺全国共同研究の提案―JASPAC(Japan Spastic Paraplegia Research Consortium)―.厚生労働省難病性疾患克服研究事業,運動失調に関する調査及び病態機序に関する研究班,平成17年度研究報告書.2006. p. 115-118. Webサイト サイト名[Internet].発表機関所在地:機関名;発表年月日[cited アクセス年月日].Available from:サイトURL.(発表年月日は分かる範囲でよい) 難病情報センター.アレルギー性肉芽腫性血管炎[Internet].東京:厚生労働省;2010 Feb 5. [cited 2011 Jan 11]. Available from: http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/005.htm. Japanese.
- 英文抄録
- 5-1.
- 英文抄録は和文要旨の英訳を記載する(和文抄録と英文抄録の内容が異なることがないようにすること).病歴等の年月日については原則記載しない.本文を読めない読者が英文単独で読んだ時にも理解できるように記載すること.原則として英語を母語としない場合は,英語のnative speakerの校閲をうけること.査読過程で編集委員が英文校閲を受ける必要があると判断した場合は,英語のnative speakerの校閲をうけることを要求する場合がある.
- 5-2.
- 英文で表題(20単語以内),著者名,学位(M.D.,Ph.D.等),所属,英文キーワード(和文キーワードと相対するもの)を記載する.
- 5-3.
- 原則としてPubMedのMesh Databaseの用語集に従う.
- Figure(写真・図)/ Figure legends
- 6-1.
- Figureは英文で記載する.引用番号/アルファベット(大文字で表記)を記載する.但し,メディカルスタッフなど医師以外の読者層が特に重要と想定される論文や,日本人読者が理解しやすいことが特に重要と考えられる論文(診療ガイドライン的なもの,日本の医療事情に関係する論文など)等の場合は和文での記載を認めることがある.
- 6-2.
- Figure は本文で必ず引用し,初出の引用は若い番号/アルファベット(大文字で表記)順に行う.
- 6-3.
- Figureは英文にて表題を付け,内容の英文説明を作成する.Clinical courseについても表題だけでなく英文説明を記載する.病歴等の年月日については原則記載しない.本文を読めない読者が英文単独で読んだ時にも理解できるように記載すること.原則として英語を母語としない場合は,英語のnative speakerの校閲をうけること.査読過程で編集委員が英文校閲を受ける必要があると判断した場合は,英語のnative speakerの校閲をうけることを要求する場合がある.
- 6-4.
- 患者が特定される身体写真(顔写真,頭部のほぼ全体がはいるものは該当.身体の一部やMRI 画像は非該当)については, 実際に掲載される画像,動画を患者が確認し,Legendsに「Fig.○ is published with patient’s permission./患者の許可を得て掲載」と記載すること.顔写真を個人が特定できないように処理する場合には,画像作成ソフトとしてAdobe PhotoshopTMで行うことを推奨する.
- 6-5.
- 画像の解像度は300dpi以上とする.
- 6-6.
- 画像には左右がわかるように記載をする.
- 6-7.
- 画像の記載例:Gd enhanced T1WI, T2WI, DWI, FLAIR, 3D TOF MRA, 123I-IMP-SPECT
- 6-8.
- MRI画像:画像の種類と静磁場強度を記載し,撮像パラメータを必要に応じて適宜記載する.
- 6-9.
- 組織標本:染色法とスケールを記載する.写真の中にscale barを入れ,英文説明に「Bar=100μm」などと示すこと.
- 6-10.
- 神経生理検査波形:脳波・誘発電位,筋電図・神経伝導検査などの神経生理検査波形を呈示する場合には,時間軸と振幅のスケール,誘導・モンタージュ(脳波・誘発 電位),刺激記録部位(神経伝導検査:必要に応じて)などを記載する.
- 6-11.
- 他紙や書籍に掲載されているFigureを転載使用する場合は,必ず転載許諾に関する手続きを経てから投稿し,Legendsに「Reprinted from the figure in the article of 文献番号 with permission. /(文献)より許可を得て転載」と記載すること.
- Table(表)
- 7-1.
- Tableは英文で記載する.引用番号/アルファベット(大文字で表記)を記載する.但し,メディカルスタッフなど医師以外の読者層が特に重要と想定される論文や,日本人読者が理解しやすいことが特に重要と考えられる論文(診療ガイドライン的なもの,日本の医療事情に関係する論文など)等の場合は和文での記載を認めることがある.
- 7-2.
- Table は本文で必ず引用し,初出の引用は若い番号/アルファベット(大文字で表記)順に行う.
- 7-3.
- Tableの英文説明は不要だが,英文で表題を付け,略語を用いた場合は欄外に記載説明する.
- 7-4.
- 他紙や書籍に掲載されているTableを転載使用する場合は,必ず転載許諾に関する手続きを経てから投稿し,欄外に「Reprinted from the figure in the article of 文献番号 with permission. /(文献)より許可を得て転載」と記載すること.
- Supplementary data(動画,文書,図表)
- 8-1.
- Supplementary dataの内容は著者責任とする.掲載に際しては本文のような校正は行わず,著者が提出した内容をそのままPDF等で掲載する.
- 8-2.
- 動画は,Windows Media PlayerあるいはQuickTimeで再生可能な動画ファイル(動画像はmpeg,mpg,mov,avi,音声はmp2,mp3,wav)で作成する.
- 8-3.
- 動画はMovie legendを作成する.英文で表題を付け,内容の英文説明を記載する.文書は英文表題のみを記載する.図表も基本的には英文表題のみとするが,英文説明をつけたい場合は,Supplementary data内に記載する.(前記のように,Supplementary dataについては査読での校正を行わないので,必要に応じて英文校閲を受けるなど,英文の質に十分留意すること).
F)投稿の方法
- 論文の投稿は,電子投稿システム「ScholarOne ManuscriptsTM」で行う.
- 投稿規程E)執筆要項に従って作成した投稿原稿以外に,以下のファイルを準備する.
- 2-1.
- 「自己申告によるCOI報告書」(必ず添付:投稿規程C参照)
- 2-2.
- 「患者同意書」(「個人情報チェックリスト」で必要と判断された場合のみ必ず添付)
- 投稿原稿ファイル,「自己申告によるCOI報告書」の準備が整ったら,「電子投稿サイト使用マニュアル」に従って投稿作業を行う.
- 修正論文を再投稿する際の注意点
- 4-1.
- 修正論文は3ヵ月以内に提出すること.3ヵ月を経過した論文は初投稿論文として取り扱う.
- 4-2.
- 「短報」から「症例報告」への書き直しを希望する場合は,初投稿の「短報」は取り下げとし.新規の「症例報告」として投稿する.タイトルの一部を変更して投稿すること.
- 4-3.
- 原稿には前回からの修正部分に下線を引く.
- 4-4.
- 査読者への回答は,各査読者のコメントごとに,どのように訂正をしたかが判るように記述する.
- 4-5.
- 査読のコメントを反映する事により,やむを得ず投稿規程の文字数を超過した場合は,査読者への回答に超過の文字数とその理由を記載する.
G)採択から掲載
- 校正段階で臨床神経学のスタイルに合わせるために,編集委員会が文言を統一した書式に書き換える.内容について著者に問い合わせをすることもある.
- 著者による校正が期間内に返却なき場合は校正の必要がないものとして公開する.なお,校正の最終責任は著者にあるので,十分に注意されたい.
- 著者による校正後,掲載予定号が公開されるまでの間,J-STAGEにて早期公開版を公開する.本誌の早期公開版は著者校正が終了したものを公開しているので,早期公開後の内容変更は認められない.
- 掲載料は5,000円とする.
- 別刷は実費負担とし,著者校正時に注文を受け付ける.
-
Full text PDFに於いて以下の頁数を超える場合,超過1頁につき10,000円の超過料を徴収する.
・総説8頁 ・原著8頁 ・症例報告7頁 ・短報4頁
但し頁超過の原因が,査読コメントに対応した為,図表を適切な大きさで掲載した為,と編集委員が判断する場合は,超過料を免除する事がある.
H)著作権について
- 本誌に掲載されたすべての論文およびその内容に係る著作権は本会に帰属する.ただし,非営利目的の場合のみ,出典(著者名,雑誌名,巻号)を明記し,引用文を挿入すれば,申請手続き無しで図表の転載利用,論文への直接リンク,ダウンロード,複写,分配することを認める(修正を加えたデータの配布は除く).
- 本誌に掲載されたすべての論文およびその内容を本会の許諾なく営利目的または商業目的で使用することを禁ずる.転載許諾手続きについては転載許諾に関する規程を参照すること.またこれによる使用料は日本神経学会に帰属するものとする.
- 本誌はオープンアクセスジャーナルであり,クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に公開している.ライセンスの詳細については以下を参照のこと.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja) - 機関リポジトリへ登録する場合は,著者が作成したオリジナルの採択原稿の使用を認める.臨床神経学掲載用に組版した原稿の使用は認めない.