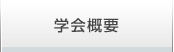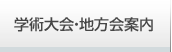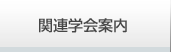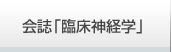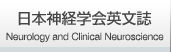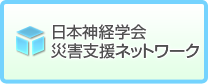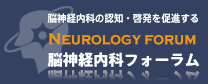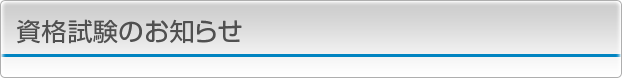2017年以前の後期研修開始者向け実施概要【旧制度】
2026年度(第52回)日本神経学会神経内科専門医試験実施概要
2026年度(第52回)日本神経学会神経内科専門医試験を下記のとおり行いますので、お知らせ致します。
2017年以前研修開始者【旧制度】、2018年~2020年研修開始者【新制度移行期】、2022年以降専門研修(2021年以降内科研修)開始者【新制度】で、提出物等に違いがありますので気を付けてください。
こちらのページは2017年以前の後期研修開始者【旧制度】向けです。
オンライン受験申請後、一部郵送提出して頂く書類がありますのでご注意ください。
第1次筆記試験(必修問題100題、一般・症例問題100題)
1 日時
2026年10月3日(土曜日)、10:30~15:10
2 場所
都市センターホテル(日本都市センター会館) 東京都千代田区平河町2-4-1
3 受験資格
2026年度 第52回 は以下のとおり。
(1)2017年以前に専門医後期研修を開始した者
(2)日本国の医師免許証を有する者
(3)受験時に初期研修を含む臨床研修期間を6年以上有するもので、かつ本学会正会員歴を3年以上有するもの
(4)日本内科学会「認定内科医(または内科専門医)」であること
(5)上記(3)の臨床研修期間について、本学会が認定する教育施設・准教育施設・教育関連施設においての神経内科研修が、次の①または②のいずれかを満たす者。
-
① 「新施設認定基準」で必要とされる研修歴は次の通りです。
なお、2021年1月31日以降、特別連携施設での研修も認められています(上限1年)。- (1)教育施設で3年以上
-
(2)教育施設2年以上かつ3年未満の場合、下記のいずれか。
a. 教育施設、准教育施設で合計3年
b. 教育施設、准教育施設、教育関連施設および特別連携施設で合計4年。
ただし、特別連携施設での研修算定期間は1年を上限とする。 -
(3)教育施設2年未満の場合
教育施設、准教育施設で合計4年(准教育施設のみで合計4年も可)
-
② 2012(平成24)年度より適用されている施設認定基準をここでは「新施設認定基準」、それ以前の施設認定基準を「旧施設認定基準」と称することとします。「旧施設認定基準」はさらに2005(平成17)年度以前の「基準B」と2006(平成18)年度から実施されている「基準B’」に分かれています。当分の間、「旧施設認定基準による教育関連施設での研修」は、「新施設認定基準による准教育施設での研修」と読み替えるものとします。
旧施設認定基準で必要とされる研修歴は次の通りです。(参考)
◎旧施設認定基準における「基準B」
初期研修を含む臨床研修期間を6年以上有するもので、次のいずれかを満たすもの。
- (1)教育施設で3年以上
- (2)教育施設で2年以上と教育関連施設で1年以上
- (3)教育関連施設で4年以上
◎旧施設認定基準における「基準B’」
初期研修を含む臨床研修期間を6年以上有するもので、次のいずれかを満たすもの。
- (1)教育施設で3年以上
- (2)教育施設で2年以上と教育関連施設で1年以上
- (3)教育施設で1年以上と教育関連施設で3年以上
研修期間を算定する場合は、一週の勤務実態は4日(32時間)以上を原則とする。
なお、研修期間として認定する勤務実態は、研修に必要な内容を伴うものでなければならない。
教育施設での非常勤勤務による研修期間は、下記に従って算定し研修期間として認定できる。
認定する研修期間は神経内科研修の最後に所属した施設の研修施設指導管理責任者(指導医)が証明書(書式・様式は自由)を提出し、その証明書を専門医認定委員会(以下「委員会」という。)が審査して認定する。研修期間は1年を超えないものとする。
- (1)週3日(24時間)の勤務実態があれば、その期間の3/4を研修期間と認定
- (2)週2日(16時間)の勤務実態があれば、その期間の1/2を研修期間と認定
- (3)週1日 (8時間)の勤務実態があれば、その期間の1/4を研修期間と認定
これらのいずれにも該当しない場合は、委員会で書類審査を行い、受験の可否を決定します。
また、外国での臨床研修についても、委員会で書類審査を行い、受験の可否を決定しますので、該当する受験者は申し出てください。
4 受験希望申出期間ならびにオンライン受験申請・郵送書類受付期間
①受験希望申出(手引きDL)期間:2026年4月13日(月曜日)~5月25日(月曜日)
MyWeb → 専門医・指導医 → 資格情報確認・申請の画面から行ってください
一度希望申出された申請区分(旧制度か移行期か新制度か)の変更はできませんので、不明点がありましたら希望申出前に事務局までお尋ねください。
②オンライン受験申請・郵送書類の受付期間:2026年6月1日(月曜日)~6月22日(月曜日)
下記6の(5)経験した疾患名、症例数および検査の記入用紙、(6)症例サマリー10例については、自署および指導医サイン済みのオリジナル書類をオンライン申請した後、郵送提出(消印有効)も必要となります。
郵送提出書類の提出部数
- 下記6(5)
-
自署・捺印をしたオリジナル1枚と、その白黒コピー4枚の合計5枚。
オリジナル作成には、MyWebの申請画面にある雛形をダウンロード(氏名と受付番号が自動印字されます)した様式を必ず利用してください。
オリジナルは、word文書にて作成したものを切り貼り可、手書きでも可。
必ず両面印刷してください。(オリジナルのみ片面印刷でも認められます) - 下記6(6)
-
10例を1部としまとめ、自署および指導医サイン済みのオリジナル1部と、その自署およびサイン済みの症例サマリーの白黒コピー4部の合計5部。
ホチキス留めはしない、クリアファイルには入れないでください。(付箋での区切りは可)
必ず両面印刷してください。(オリジナルのみ片面印刷でも認められます)
郵送提出書類の提出先
「書留郵便」を利用してお送りください。(消印有効)(レターパックプラスでも可)
- 提出先:
-
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-21 一丸ビル2階
日本神経学会事務局「第52回神経内科専門医試験「旧制度」受験申請」係
5 第1次筆記試験受験料
30,000円
お振り込みについては、オンライン受験申請(申請ボタンを押下)後に案内が表示されます。
6 オンライン受験申請に必要な提出書類(6種類)
- (1)医師免許証の写し
- (2)顔写真
- (3)ミニマムリクアイアメント達成状況表
- (4)研修修了証明書(旧制度)
- (5)経験した疾患名、症例数および検査の記入用紙※1
- (6)症例サマリー10例※2
上記(3)(4)の様式は、それぞれリンクからダウンロード可能です
※1経験した疾患名、症例数および検査の記入用紙
この様式については、MyWebの申請画面にある雛形をダウンロードしたものを必ずオリジナルとして使用してください。(氏名と受付番号が自動印字されるようになっています)
●神経疾患の分類:
①血管障害、②感染、炎症、③変性、④脱髄、⑤中毒、⑥代謝、⑦腫瘍、
⑧機能性、⑨先天性、⑩脊髄・脊椎、⑪末梢神経、⑫神経筋接合部および筋、⑬自律神経、⑭その他
●経験症例数:
各疾患名の後に経験症例数を( )で附記すること。
記入例:
①血管障害:心原性脳塞栓症(30)、アテローム血栓性脳梗塞(30)、ラクナ梗塞(30)、
脳出血(10)、クモ膜下出血(5)、その他(8)など
●神経学的検査:自らが実施した数を記入してください。
記入例:
脳波(検査の実施数:20 、結果の判読数:100)
剖検(例数:5)
●「0」という記載はしないよう、自身の担当症例でなくても良いので、少なくとも1件は、指導医に十分に指導をしてもらいながら実施・判読を行ってください。
●症例数が多く疾患名を記入しきれない場合は、別紙(A4)を追加し記入してください。
※2症例サマリー10例(書き方見本【旧制度】・書式テンプレートDL(ID・PW必要))
●使用用紙:1症例につきA4サイズで2ページ。
●使用活字:MSP明朝で11ポイント、1行文字数40字程度、2,500字前後。
●スタイル:
まず、各提出症例に1~10の番号をつけてください。
最初に「症例のポイント」、「臨床診断」を、次いで主訴、既往症、家族歴、現病歴、一般身体所見、神経学的所見、所見のまとめ、診断に関する考察、主な検査所見、経過、考察の順に記載すること。現病歴での年・月はX年Y月ではなく具体的に記載し、日の特定は避けてください。最後に文字数を記載、及び指導医のサインをもらってください。
●症例内容:
特定の疾患に偏ることなく、できる限り神経疾患の分類①~⑭の異なる分野から症例を選ぶように努め、また剖検例も出来る限り含めてください。
●症例サマリーは査読を行い、査読者が不可と判定した場合には、修正の上再提出を求めます。
採点結果は、第2次面接試験の際に資料として用いられます。
●誤字、脱字、漢字の変換ミス、あるいはコピーペーストが不適切なサマリーが目立ちますので、提出前に必ず点検してください。
7 第1次筆記試験案内
8月下旬を目安に、筆記試験受験決定者へメール通知(受験番号通知)致します。MyWebからの「受験票DL」が利用可能となります。
8 第1次筆記試験合否結果
試験終了後10日以内にMyWeb内にて通知致します。
第1次筆記試験問題概要
後に記すような問題が必修問題100題、一般問題・長文の症例問題を合わせて100題の合計200題が出題されます。解答形式は必修問題はAタイプのみ、一般・症例問題はAタイプとX2タイプのいずれかです。
例1)上腕外側上部領域の表在感覚を支配する脊髄髄節はどれか(Aタイプ)。
a)C4
b)C5
c)C6
d)C7
e)C8
例2)正中神経の支配筋の機能はどれか。2つ選べ(X2タイプ)。
a)母指を小指と対立させる
b)母指を示指に押し付ける
c)母指を背側に伸展させる
d)母指を掌面に垂直に立たせる
e)母指を掌面に平行に外転させる
第2次面接試験(口頭・実技試験)
1 日時
2026年11月8日(日曜日)、面接試験時間は受験者個別にメール通知。
2 場所
都市センターホテル(日本都市センター会館) 東京都千代田区平河町2-4-1
3 第2次面接試験の受験申請・受験料
第1次筆記試験合格者のMyWeb画面から、受験申請(第2次面接試験受験料20,000円のお支払い)が可能となります。
お振り込み確認完了次第、第2次試験用の「受験票DL」が利用可能となります。
4 第2次面接試験の時間と結果通知
個別面接試験時間は、10月下旬を目途にMyWebに登録されているメールアドレス宛てに配信、合否は、試験終了後2週間以内にMyWeb内にて通知致します。
5 専門医登録料
10,000円
6 専門医資格(認定期間)の証明
合格者氏名は臨床神経学ならびにホームページに公示し、「日本神経学会認定証」を後日(2027年2月目途)宅急便にて発送します。
ただし、「日本神経学会認定証」には認定期間の記載がありませんので、認定期間の証明については、MyWebの資格情報画面にてご確認頂くか、証明書PDFを発行致しますので、必要時に事務局までご連絡をお願い致します。
第2次面接試験概要
第2次面接試験はA組、B組の2種類あり、それぞれ時間は20分で、面接員は2名です。
A組では、神経内科の診察実技が主体になりますので、必ず自分の診察道具(眼底鏡、ペンライト、舌圧子、打腱器、感覚検査用具一式など日常使用しているもの)を持参してください。また、B組では、神経学に関する知識を、経験症例に基づいて試問しますので、症例サマリー10例のコピーを必ず持参してください。
第2次面接試験のみ受験(第1次筆記試験免除)となる方
2025年度第51回、2024年度第50回、2023年度第49回、2022年度第48回、2021年度第47回の試験で、第1次筆記試験は合格、第2次面接試験が不合格となった方で「認定内科医(または内科専門医)」を取得している方が対象となります。その後の5年間で3回まで第1次筆記試験が免除されます。
受験申請においては、研修修了証明書【旧制度】およびミニマムリクワイアメント達成状況表の提出は免除されます。
対象者は、4月13日(月)より、MyWeb → 専門医・指導医→ 資格情報確認・申請 画面より手引きの確認・ダウンロード、下書き保存が可能となります。その後、6月1日(月)~6月22日(月)のオンライン申請・郵送書類の受付期間で、受験申請および郵送書類の提出を行ってください。
第2次面接試験の個別面接試験時間は10月下旬を目途にメール配信致します。